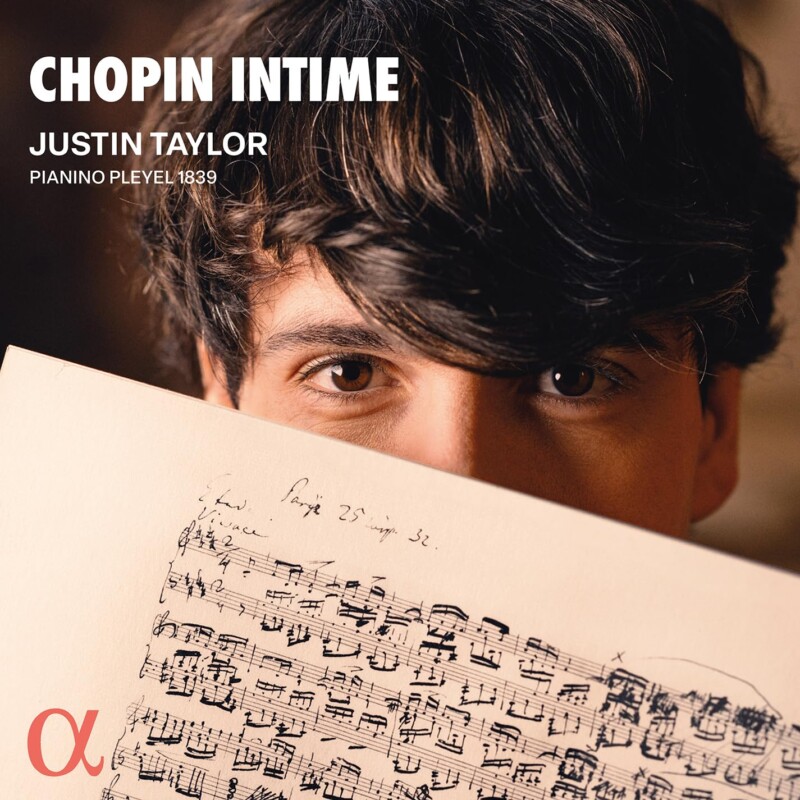今年はベートーヴェン生誕250周年に当たり、長く絶版になっていたジュリアード弦楽四重奏団による弦楽四重奏曲全集が再リリースされた。1964年から70年にかけての彼らの最初の全曲演奏で、第1ヴァイオリンのロバート・マンら4人の名手による演奏は、半世紀たっても輝いている。
ベートーヴェンが死の前年まで書き続けた弦楽四重奏曲というジャンルでは、個人的な真情の表現と古典派の形式を極限まで推し進めようとした彼の音楽の軌跡をたどることができる。第1番のアダージョの最後に、チェロやヴィオラが朗々とテーマを歌うなか、ヴァイオリンが悲痛な叫びを奏でる部分の緊張感は、ジュリアードならでは。ハイドンやモーツァルトには書けなかった、4つの楽器が絶えず対話を交わし葛藤していく世界が広がる。第7番のアダージョの悲しみ、13番の『カヴァティーナ』での微妙な和声の美しさ…。そして『大フーガ』。耳に快いかどうかは関係ない、「常に本質をのみ語れ」といったベートーヴェンの、15分以上続く不協和な荒々しいフーガは、バルトークすら超えることができなかった。ジュリアードの全身全霊をこめた演奏から生命力がほとばしる。(真)